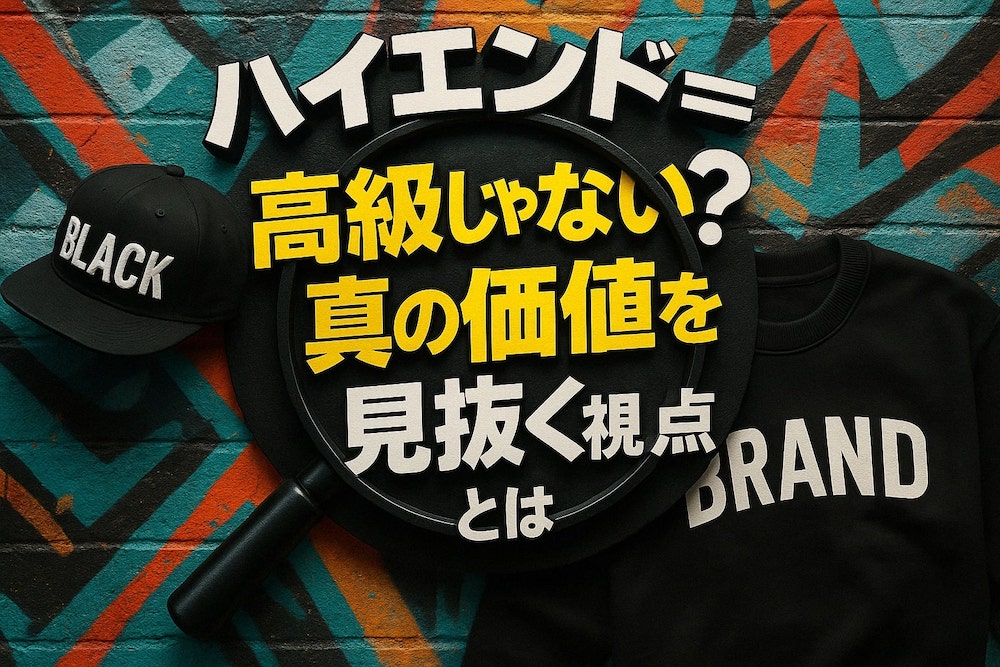「高級ブランド」という言葉を聞いて、あなたは何を思い浮かべるだろうか。
おそらく多くの人が、LVやGucciといった誰もが知るラグジュアリーブランドの華やかなロゴを想起するのではないか。
だが、「高級=ハイエンド」という図式は、現代のファッションシーンにおいて、すでに色褪せた概念になりつつある。
今この瞬間も、価格ではなく「価値」にこだわる新しい消費者たちが、従来の高級概念を解体し、再構築している。
私が裏原宿カルチャーに身を置いていた90年代後半、僕らもまた「真の価値」を追い求めていた。
それは単に高価格というだけではなく、服が語る物語や、着こなす人のスタイル、そしてカルチャーとしての奥行きだった。
いま、その感覚が再び重要性を増しているのを感じる。
ストリートカルチャーの視点から見れば、真にハイエンドなものとは何か。
それは価格タグの数字ではなく、むしろ「見る目」を持った人だけが認識できる価値のことではないだろうか。
この記事では、私が30年近くファッションシーンを渡り歩いてきた経験から、真の価値を見抜くための視点を共有していきたい。
参考: HBSのハイエンド・ストリートウェアブランドが話題!
ハイエンドとは何か?─定義の解体
「高価格=高級」の罠
「これ、いくらしたの?」
ファッションの会話でよく耳にするこの質問は、私たちがいかに価格と価値を混同しているかを端的に表している。
高価なものは必ずしも価値が高いとは限らないし、逆に言えば、適正な価格のものが価値を持たないわけでもない。
価格が価値の代替指標として機能していた時代は、情報が限られていた過去の話だ。
現代の情報過多社会では、価格という指標だけに依存するのは危険であり、それはむしろ「思考停止」の表れだと言える。
ロゴが目立つだけの既製品に高額を支払うことが、本当の意味で「ハイエンド」な消費といえるだろうか。
そこには「わかりやすさ」以外の価値はあるのだろうか。
私が90年代にBEAMSで働いていた頃、本当の目利きたちは、ブランド名すら付いていない無名の古着や、小さな工房で作られた品物に価値を見出していた。
彼らは価格ではなく、デザインの独自性、素材の質感、作り手の哲学、そして着る人との調和を見ていたのだ。
このような「目利き」の感覚こそが、本来のハイエンドを支える基盤だったはずだ。
ラグジュアリーとカルチャーのねじれた関係
ラグジュアリーとストリートカルチャーは、かつて水と油のような関係だった。
しかし2010年代以降、両者の境界線は急速に曖昧になってきている。
ルイ・ヴィトンとシュプリームのコラボレーション、ヴァージル・アブローのオフホワイトからルイ・ヴィトンのメンズ部門へのディレクター就任など、象徴的な出来事は数多い。
この現象は、単にラグジュアリーブランドがストリートの要素を取り入れたということだけではない。
それは、価値の定義そのものが変化したことを意味している。
「ラグジュアリーストリート」という新たなカテゴリーの誕生は、両者の融合というよりも、価値観の根本的な変容を表している。
しかし、この変容の中で失われていくものにも、私たちは目を向けるべきだ。
ラグジュアリーブランドがストリートの美学を取り入れる一方で、ストリートカルチャーの本質である「反骨精神」や「自己表現」の側面は、商業主義の中で希薄になっていることも否めない。
文化の交差点で起きているのは、単なる融合ではなく、本質と表層の複雑な交錯なのだ。
裏原世代が体感してきた「価値」のリアリティ
1990年代後半の裏原宿は、新しい価値観が生まれる実験場だった。
そこには、ブランドの名前よりも「センス」や「知識」が評価される独自の生態系が存在していた。
ブランドロゴが目立つ服よりも、誰が何をどう着こなすかという「コンテキスト」が重視された時代だった。
私がBEAMSで働いていた当時、お客さんとの会話は単なる接客ではなく、カルチャーシェアの場でもあった。
「この服はあのDJが着ていたやつだ」「このTシャツはあのアーティストがライブで着てた」といった文脈が、商品に新たな価値を付加していた。
価値とは、服そのものに内在するだけでなく、着る人と着られ方のストーリーの中にこそあった。
裏原で育まれた価値観は、単なるファッションの問題を超えて、生き方そのものに関わるものだった。
無名でも質の高いもの、大量生産ではなく少量生産のもの、誰でも持っているものよりも個性的なものを選ぶというライフスタイルの選択だった。
この価値観は、表参道や代官山などの華やかな商業地区ではなく、あえて「裏」の路地に息づいていたからこそ、純度を保っていたのかもしれない。
ストリートが教えてくれた価値の基準
ブランドではなく「誰がどう着るか」
ストリートカルチャーの真髄は、「何を着るか」よりも「どう着るか」にある。
同じTシャツでも、着る人によって全く異なる印象になるのは、服そのものよりも、着こなしや組み合わせ、そして何よりも身に纏う人のオーラや所作が重要だからだ。
私の恩師は「服は着る人次第で価値が10倍にも10分の1にもなる」とよく言っていた。
本当のスタイリッシュさとは、高級ブランドのアイテムを揃えることではなく、自分自身の個性や生き方を表現できているかどうかにある。
しばしば目にする「全身ブランドコーディネート」は、逆説的に言えば着る人の個性の欠如を露呈しているとも言える。
それは服によって着られているような、主体性の喪失した状態ではないだろうか。
90年代にスケーターたちがバギーパンツを着こなしていた姿、ヒップホップカルチャーから派生したオーバーサイズの美学、DJたちのシンプルながらもエッジの効いたスタイル。
それらはいずれも、「ライフスタイルの延長線上にあるファッション」という本質を体現していた。
ストリートは常に「着る人」と「着方」が価値の中心にあったのだ。
ストーリーと文脈が価値を生む
ファッションの真の価値は、目に見える服そのものだけでなく、その背後にあるストーリーとコンテキストにある。
例えば、一見シンプルに見えるレイヤリングの中に、デザイナーのこだわりや職人の技術、素材のサステナビリティに関する考え方といった無数の物語が詰まっている。
そしてそれを理解できる「文脈の共有」こそが、真の価値を認識するための鍵となる。
私が1990年代に初めて目にしたAPE®の初期作品や藤原ヒロシのサンプル品には、単なる「服」を超えた物語があった。
それは裏原宿という特定の場所と時代、そこに集まった人々の思想や美学、音楽やアートとの結びつきという文脈の中でこそ、その本当の価値が理解できるものだった。
服は単なる布の組み合わせではなく、カルチャーの結晶として存在していたのだ。
現代においても、本当の価値を持つ服には必ずストーリーがある。
それはデザイナーの哲学かもしれないし、素材の調達方法かもしれない。
あるいは、その服が着られてきた歴史や、着る人々のコミュニティの物語かもしれない。
こうした無形の要素こそが、真のハイエンドを定義するのだ。
自己表現としての服、反骨としてのスタイル
ストリートファッションの本質は、常に「反骨精神」と隣り合わせだった。
それは単に既存の価値観への反発という消極的なものではなく、自分たちの新しい価値観を積極的に表現していくという創造的な行為だった。
だからこそ、ストリートファッションは常に時代の一歩先を行き、新しいカルチャーの萌芽となりえたのだ。
1980年代のスケーターたち、1990年代のヒップホップカルチャー、2000年代のインディーズシーン。
彼らはいずれも、ただ流行を追いかけるのではなく、自分たちの生き方の表現としてファッションを捉えていた。
そこには、「服を着る」という行為を通じた明確な自己表明があった。
私自身、20代の頃は意識的に当時の主流とは異なるスタイルを追求していた。
それは単なる差別化欲求ではなく、自分自身のアイデンティティを模索する旅のようなものだった。
服を通して問いかけていたのは「自分とは何者か」という根源的な問いだったのかもしれない。
真に価値のあるファッションとは、このような自問自答のプロセスから生まれるものではないだろうか。
真の価値を見抜くための視点
所作・言葉・素材──「見えるもの」の奥にあるもの
真の価値を見抜くためには、服そのものだけでなく、それを身に纏う人の「所作」にも目を向ける必要がある。
どれだけ高価な服でも、着る人の立ち振る舞いがそれに伴っていなければ、違和感を生じさせるだけだ。
逆に、シンプルな服でも、着る人の佇まいや動きに品があれば、その全体像は美しい調和を奏でる。
言葉遣いも重要な要素だ。
私はインタビュー記事を書く際、対象者の服装だけでなく、その話し方や言葉選びにも注目している。
言葉は思考の表れであり、その奥にある価値観を映し出すからだ。
真に価値のあるスタイルを持つ人は、たいてい言葉にも独自性と深みがある。
そして素材。
これは物理的に「見えるもの」ではあるが、多くの人が見落としている重要な要素だ。
質の高い素材は、着る人の肌の上で経年変化し、独自の表情を見せていく。
大量生産された合成素材と手織りの天然素材では、時間の経過とともにその差は明らかになる。
真の価値は、このような「時間の試練」に耐えうるものの中にこそ宿るのだ。
服が語る「生き方」と「哲学」
真に価値のある服には、必ずそれを支える「生き方」や「哲学」が存在する。
それは単なるデザインの問題ではなく、より根本的な世界観や価値観の表れだ。
例えば、サステナビリティを重視するブランドであれば、その姿勢は素材選びから製造プロセス、流通方法に至るまで一貫している。
私が尊敬するデザイナーたちは、服を通して自分の哲学を表現している。
彼らにとってファッションは単なるビジネスではなく、自分の世界観を形にする媒体なのだ。
そのような真摯な姿勢から生まれた服には、言葉では表現できない深みがある。
GLOWSTを立ち上げた際、私自身も「服づくりとは何か」を改めて問い直した。
それは単に「かっこいいもの」を作ることではなく、自分が信じる価値観や美学を形にすることだった。
服は単なる商品ではなく、メッセージであり、問いかけであり、対話の糸口なのだ。
そのような視点を持てば、ただの「モノ」としての服を超えた価値が見えてくるはずだ。
都市文化における”ノイズ”の読み解き方
都市の雑踏の中には、無数の「ノイズ」が存在する。
それは一見すると無秩序で混沌としたものだが、そこから新たなカルチャーの兆しを読み取る力こそ、真の価値を見抜くために不可欠な感性だ。
90年代の裏原宿は、まさにそんな「ノイズ」の集積地だった。
大手ブランドがまだ注目していない時代に、若者たちは独自のカルチャーを育んでいた。
DJブースの横に並ぶレコード、ローカルスケーターの着こなし、アーティストのアトリエに置かれた本。
そうした「ノイズ」の中に、次の時代を予感させる価値の萌芽が潜んでいた。
真の目利きとは、このノイズの中から意味のあるシグナルを拾い上げる能力を持った人だ。
それは単なる情報収集能力ではなく、カルチャーの深層を感じ取る感性であり、時代の空気を読む直感だ。
市場調査やトレンド分析では決して得られない、人間としての感受性に基づく判断力なのだ。
この「ノイズ」への感度こそが、真の価値を見抜く目を養うのではないだろうか。
ハイエンドと大衆性の狭間で
商業主義が奪う”本当のラグジュアリー”
皮肉なことに、本来のラグジュアリーが持っていた「希少性」や「唯一無二の価値」は、商業主義の浸透によって徐々に薄れてきている。
かつてラグジュアリーブランドは、限られた層のための特別な存在だった。
しかし、グローバル展開と大量生産化により、その特別感は次第に失われつつある。
私が特に懸念するのは、「ブランド」という記号が「価値」そのものにすり替わっている現象だ。
ロゴが目立つアイテムが高く売れる時代に、デザインや素材、作りの質といった本質的な価値は軽視されがちだ。
これは本来のラグジュアリーの定義からすれば、本末転倒とさえ言える状況ではないか。
真のラグジュアリーとは、大量生産されたものとは一線を画す唯一無二の存在であるはずだ。
職人の手仕事による微妙な個体差、天然素材がもたらす表情の豊かさ、時間とともに育まれる経年変化。
こうした要素こそが、本来のラグジュアリーの核心だったのではないだろうか。
商業主義の波に飲み込まれない、この本質的な価値への眼差しを、私たちは失わないようにしたい。
消費と共感──現代ストリートの危うさ
現代のストリートファッションには、かつてのような反骨精神や自己表現というコアな部分が失われつつあるように感じる。
SNSの普及により、かつては裏原宿のような特定のコミュニティでしか共有されなかった情報が、瞬時に世界中に拡散する時代となった。
これにより、「知る」ことと「理解する」ことの間に大きな溝が生まれている。
Z世代のファッション消費においては「コミュニケーションツール」としての側面が強く、約70%が「遊びに行く場所に合わせる」と回答している。
彼らにとってファッションは自己表現ツールというより、むしろ特定のコミュニティや状況に合わせて変化させる適応手段となっている。
この現象自体は否定すべきものではないが、それがストリートカルチャーの本質である「個」の表現や「反骨精神」を希薄化させる可能性もある。
また、SNSの影響により「界隈消費」という現象も生まれている。
これは特定のファッション界隈(「ノームコア系」「韓国系」「ストリート系」など)でのみ支持されるものに価値を見出す消費傾向だ。
この現象は個性の表出という点では評価できるが、反面、その「界隈」内でのみ通用する記号的な消費に陥るリスクも孕んでいる。
真の価値とは、そうした一時的なコミュニティの枠を超えて、普遍的に認められるものではないだろうか。
コレクター精神と”日常使い”のバランス
ファッションにおける価値を考える上で、「コレクターアイテム」と「日常使い」のバランスは非常に重要だ。
希少なヴィンテージや限定アイテムを所有する喜びは特別だが、それが日常から切り離されたコレクション対象にとどまるなら、その価値は限定的である。
真に価値のあるものとは、特別な存在でありながらも、生活に溶け込み、時間とともに育まれていくものではないか。
私自身、30年以上かけて集めてきたヴィンテージアイテムの中には、ケースに入れて保管しているものと、実際に着用しているものがある。
後者は経年変化によって独自の風合いを獲得し、私自身のストーリーと一体化している。
このような「生きた関係」こそが、本当の意味での価値を生み出すのではないだろうか。
若い世代にアドバイスするとすれば、「保存」と「使用」のバランスを意識してほしいということだ。
確かに希少価値のあるアイテムを未使用の状態で所有することには価値があるが、それと同時に、実際に身に着け、時間をかけて自分だけの一着に育てていく体験もまた、かけがえのないものだ。
そこには金銭では測れない、着る人と服との対話から生まれる価値がある。
このような「関係性の価値」こそ、真のハイエンドの本質なのかもしれない。
若い世代は何を価値と見るのか?
Z世代と価値観のすれ違い
Z世代(1995年〜2010年生まれ)は、デジタルネイティブであり、生まれたときからインターネットとスマートフォンのある環境で育ってきた世代だ。
彼らのファッション消費の特徴は、ブランドそのものへのこだわりよりも、個人の価値観や場面に合わせた選択を重視する傾向にある。
調査によれば、約70%のZ世代がブランドよりもファッションテイストを重視し、特定のブランドへの執着が低いことが報告されている。
これは私たち裏原世代が育んできた価値観とは、微妙に異なる点がある。
私たちが「カルチャーとしてのブランド」に価値を見出してきたのに対し、Z世代はより機能的な視点で「自分に似合うか」「場に合っているか」を判断基準にしている。
彼らは骨格診断やパーソナルカラーの分析など、より「科学的」なアプローチでファッションを選択する傾向にある。
しかし興味深いことに、Z世代も「自分らしさ」や「個性」を重視するという点では共通している。
違いは、その表現方法だ。
私たち世代が特定のカルチャーやブランドへの共感から自己表現を行ったのに対し、Z世代はより多様な選択肢の中から「自分に合うもの」を選び取る、という姿勢が強い。
このような価値観のすれ違いを理解することが、世代を超えた対話の第一歩になるのではないだろうか。
ソーシャルメディアが変える「評価軸」
SNSの普及は、ファッションの「評価軸」そのものを大きく変えた。
かつては実際の着こなしや街での見え方が重視されていたが、今ではSNS上での見え方が優先される場面も多い。
Z世代の約70%が「遊びに行く場所に合わせる」と回答している背景には、SNS投稿を前提としたファッション選びという現実がある。
写真映えするデザイン、色の組み合わせ、全身コーディネートのバランス。
これらは確かに視覚的な価値判断として重要だが、服の着心地や素材感、経年変化といった身体的・時間的な価値は、SNSでは伝わりにくいという課題がある。
情報伝達が視覚に偏重するSNS文化の中で、真の価値をどう伝えていくかは、現代のファッション業界の大きな課題だ。
また、Z世代に特徴的なのは「界隈消費」という現象だ。
これは特定のファッション界隈(「ノームコア系」「韓国系」「ストリート系」など)内での評価を重視する消費行動である。
「界隈」内での共感や承認を得ることが目的化し、その範囲内でのみ通用する価値基準が作られている。
これは一面では多様性の表れとも言えるが、その反面、より普遍的・長期的な価値観の形成が難しくなっているとも言える。
真の価値とは、特定の「界隈」を超えて、時代を超えて認められるものではないだろうか。
どうすれば本質は伝わるのか?
若い世代に真の価値を伝えるためには、単なる「教え」ではなく、体験を通じた「気づき」の機会を提供することが重要だ。
例えば、質の高い素材や職人技術の素晴らしさは、言葉で説明するよりも、実際に手に触れ、身に着けることで実感できるものだ。
そのような直接体験の場を意識的に作り出すことが、世代を超えた価値の継承につながるのではないだろうか。
また、Z世代の強みである情報収集力と、私たち世代の強みである文脈的理解を組み合わせることも効果的だ。
例えば、単にヴィンテージアイテムの希少性を強調するのではなく、そのアイテムが生まれた時代背景や文化的意義、デザイナーの思想など、より深い文脈を共有することで、より豊かな価値の理解が可能になる。
そして最も重要なのは、「対話」だ。
一方的に価値観を押し付けるのではなく、互いの視点を尊重しながら対話を重ねることで、新たな価値の地平が開ける可能性がある。
私自身、若手デザイナーやスタイリストとの対話から多くのことを学んでいる。
真の価値とは、固定されたものではなく、世代を超えた対話の中で常に更新され、深化していくものなのかもしれない。
まとめ
「高級」と「価値」は同義ではない。
この単純な事実に立ち返ることが、現代のファッションシーンを読み解く鍵になると私は考えている。
高価格帯のアイテムが必ずしも価値が高いわけではなく、またその逆も然りだ。
真の価値とは、価格タグではなく、デザインの独自性、素材の質感、作り手の哲学、そして何より、着る人との調和の中に宿るものだ。
自らの視点を研ぎ澄ますことの重要性も強調しておきたい。
あふれる情報と商品の中で、自分自身の価値観を持ち、それに基づいて選択することは、単なる消費行為を超えた創造的な営みとなる。
それはファッションを通した自己表現であり、自分らしい生き方の模索でもある。
このような主体的な姿勢こそが、真の意味での「目利き」を育むのではないだろうか。
ストリートカルチャー的審美眼の再評価も、今後重要になってくるだろう。
かつてストリートカルチャーが持っていた「反骨精神」や「自己表現」という本質的な価値は、現代のファッションシーンでも十分に通用する。
むしろ、商業主義とSNS文化が支配的な現代だからこそ、そのような本質に立ち返る動きが生まれているのではないだろうか。
最後に、真の価値とは時代や流行を超えて存在するものだということを強調しておきたい。
それは単なるトレンドやブームではなく、時間の試練に耐え、着る人と共に成長していくものだ。
そのような視点で選んだアイテムは、数年後、あるいは数十年後も、あなた自身のアイデンティティの一部として輝き続けるだろう。
それこそが、私が考える真のハイエンドの姿なのだ。